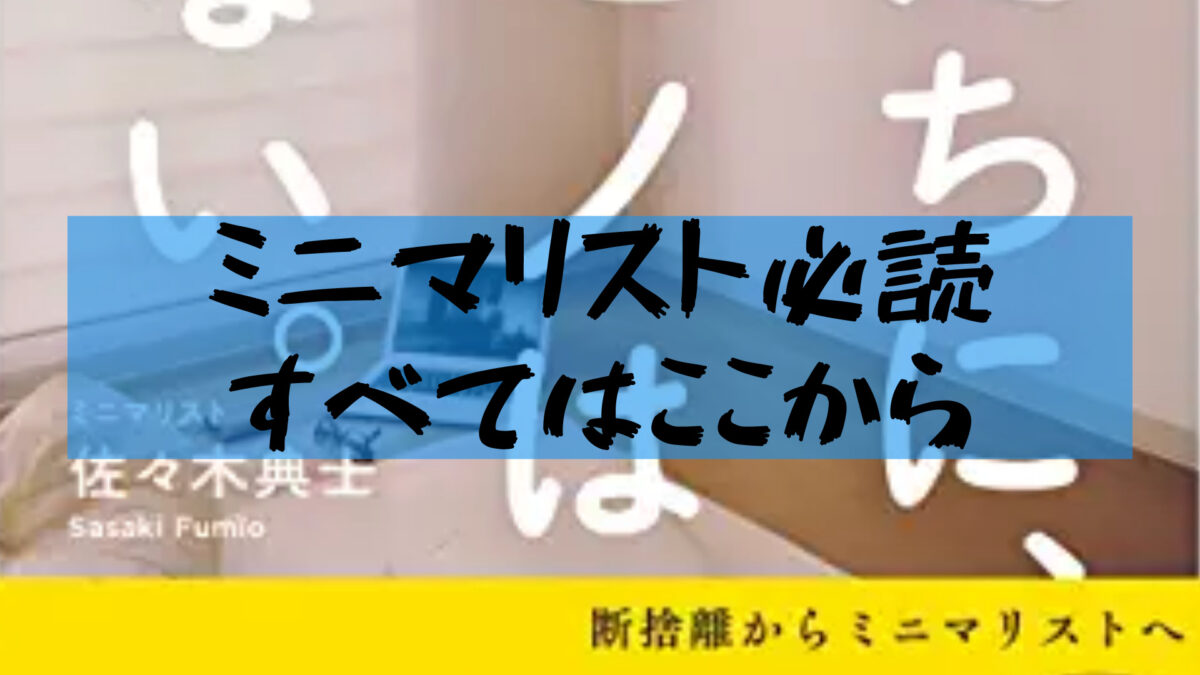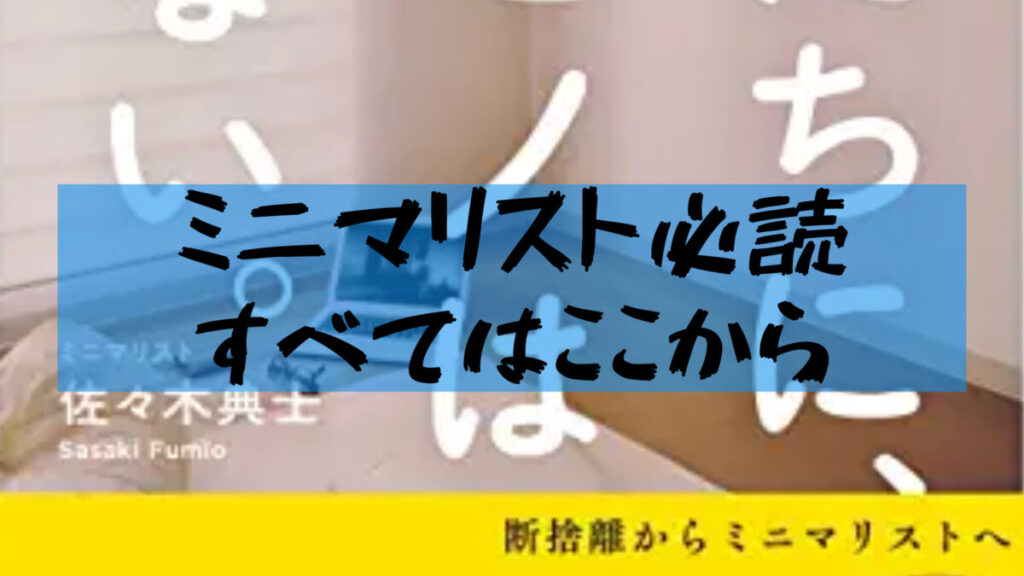
高校生のころ「ミニマリスト」を初めて知り、考えに惹かれてミニマリストについて調べるように。
その中でミニマリストおすすめ本として名前が挙がる、本作品について実際に読んでみました。
今回は佐々木典士さんの「ぼくたちにもうモノは必要ない。」の内容と感想を書いていきます!
ぼくたちにもうモノは必要ない。 情報
筆者:佐々木典士
1979年生まれ。香川県出身。学研『BOMB』編集部、『STUDIO VOICE』編集部、ワニブックスを経てフリーに。初の著書『ぼくたちに、もうモノは必要ない。』(ワニブックス刊)は16万部突破、20カ国語へ翻訳。
https://minimalism.jp/121-2
あらすじ
かつて自分が人生において「負け犬」だと感じていた筆者は今までの挫折経験を振り返ってみる。
すると多くの事柄について、モノにとらわれた価値観が負の感情につながっていたことに気づく。
目に見えるものだけではない、人生において本当に大切なモノを考え直すことができた。
モノを捨てることで得られた幸せや、モノが少ないことの利点、ミニマリストの考え方を紹介する。
ぼくたちにもうモノは必要ない。内容
誰もがミニマリストだった
縄文時代の”生きるのに必要なモノ”だけ生活から、娯楽など”生きるのに必要ないモノ”が現れました。
現代では生きるのに必要のないモノが多すぎて、本当に必要なモノなのか判断できなくなっています。
かつての縄文時代のように何もない生活に戻ることで、モノのありがたさを知ることができます。
何もない畳の上に寝転がることや、小ざっぱりした旅館に行くことで心が落ち着くのもそれに近いもの。
筆者が処分したもの
筆者は見栄を張るためにたくさんモノを所有するマキシマリストで、処分したモノがなかなかすごい。
ここには書けないようなモノも大量に処分したとのことで、お金と空間をモノが奪ういい例です。
- 本を本棚ごと(100万円以上)
- コンポとCD
- エレキギターとアンプ
- アンティークの雑貨
- 42型テレビ
- カメラ用品一式(暗室もあったそう)
- 自転車とたくさんの工具 etc.
ミニマリストと禅
処分品から著者の多趣味がうかがえますが、中には見栄で購入し一度も触れていないモノもあるとか。
縄文時代にまでさかのぼらなくても、日本人の心はミニマリストに通ずる「禅」という考えがあります。
ミニマリストが好きなアップル製品は、日本の「禅」を意識してデザインされ逆輸入されるように。
創設者のスティーブ・ジョブズも同じ種類の服を着る、商品や会社に最小限を目指したのは有名な話です。
ミニマリストは手段
ミニマリストとはあくまでも、それを通して自分にとって大切なものを見つけるための手段です。
手段であることを忘れてミニマリストになることを目的にすると、モノを減らすことに病的になります。
ただモノを減らして喜ぶだけの日々になったり、他人の持ち物にまで干渉するようになるので注意です。
現代に氾濫する情報
社会の情報量は増え続ける一方で、人間はもちろん、コンピューターですら処理に苦労しています。
増え続ける情報量に対し、我々は5万年前からさほど進化していない古いハードウェア「脳」を用いています。
古いハードに大量の情報を入力しても、情報をきちんと処理して正しく動くことを期待するのは難しい。
モノを捨てるということは、それに付随する情報も捨てるということを意味しています。
モノが少なければ、それについての選択や心配をする必要がなく、別のことに考えを使えるように。
「欲しいもの」がなくならない理由
我々は”モノに飽きる”性質を持つため、どんなお金持ちでも欲しいものを全て手に入れることはできません。
かつておもちゃの指輪で喜んでいた女の子は、成長しどんなに大きなダイヤの指輪にも満足できなくなります。
欲しいものがなくならない不満から逃れるための唯一の方法は「現状に満足すること」。
今あるモノに満足し生活に満足すれば、どんなにたくさんのモノを持つ人よりも幸福になれます。
いらないものの正体
ミニマリストになるために出てくる必要ないものの多くは「自分の価値」を伝えるためのものがほとんどです。
人の内面はその人と長く付き合わないとわかりませんが、持っているものでなら価値はすぐに伝わります。
例)この人はたくさん本を持っているから知識が豊富な賢い人に違いない
初対面での印象が大切なこともあり、このような考え方が間違っているとは言いません。
ただ自分を伝えるための持ち物が多すぎると、きっと最後には自分を苦しめることになるでしょう。
ミニマリストになる方法
後半は実際にミニマリストを目指す人のために、いらないものを捨てる方法が紹介されています。
今回はそのうちで私が「なるほど」と思い、実際に使ってみた考え方を紹介していきます。
- 捨てられないという思い込みを捨てる
- 「今」捨てることがすべての始まり
- 捨てて後悔するものは一つもない
- 人の目線ためにあるものは捨てる
- 街があなたの「間取り」です
- 熱く語れないものは捨てる
- レンタルできるものはレンタルする
- 捨てたからといって忘れない
- 物を減らしても自分は減らない
- ものが少ない対決をしない
ミニマリストのメリット
メリットの中から私が「これは!」と思えるものを3つ選んでみました。
時間ができる
モノが少ないからそれらにかかる時間も少なくて済みます。
掃除がその顕著な例。
モノがある:「ものどける」→「拭く」→「元に戻す」
モノがない:「拭く」
行動的になれる
持ち物が少ないから何かやりたいことがあった時にすぐに実行に移すことができます。
普通の人は荷造り、サービスの解約、いらないものの処分など、かなりエネルギーを使います。
内向的なタイプが多いと言われるミニマリストですが、モノが少ないことで活動的にもなりえます。
「今」、「ここ」を味わえる
マインドフルネスでも存在する考え方「今、ここを感じる」。
過去の懐かしいもの、未来の心配をしなければならないもの、に縛られると現在を楽しめません。
過去や未来に関するモノの所有はほどほどにして、今を生きることを大切にしましょう。
ぼくたちにもうモノは必要ない。感想
最近は白黒でシンプルなミニマリスト本が多いですが、個人的にこっちのほうが好きです。
表紙をめくったところからカラー写真があって楽しい!
本ブログのミニマリスト記事では「物」を「モノ」と表記することが多いですが、この本の影響です。
それだけにこの本は私にとって大きな存在となっていると言えます。
モノの捨て方がリスト化されているという点で、ミニマリストになろうと考える方にもおすすめです。
ミニマリストなら一度は読んでおくべき本ではないでしょうか?